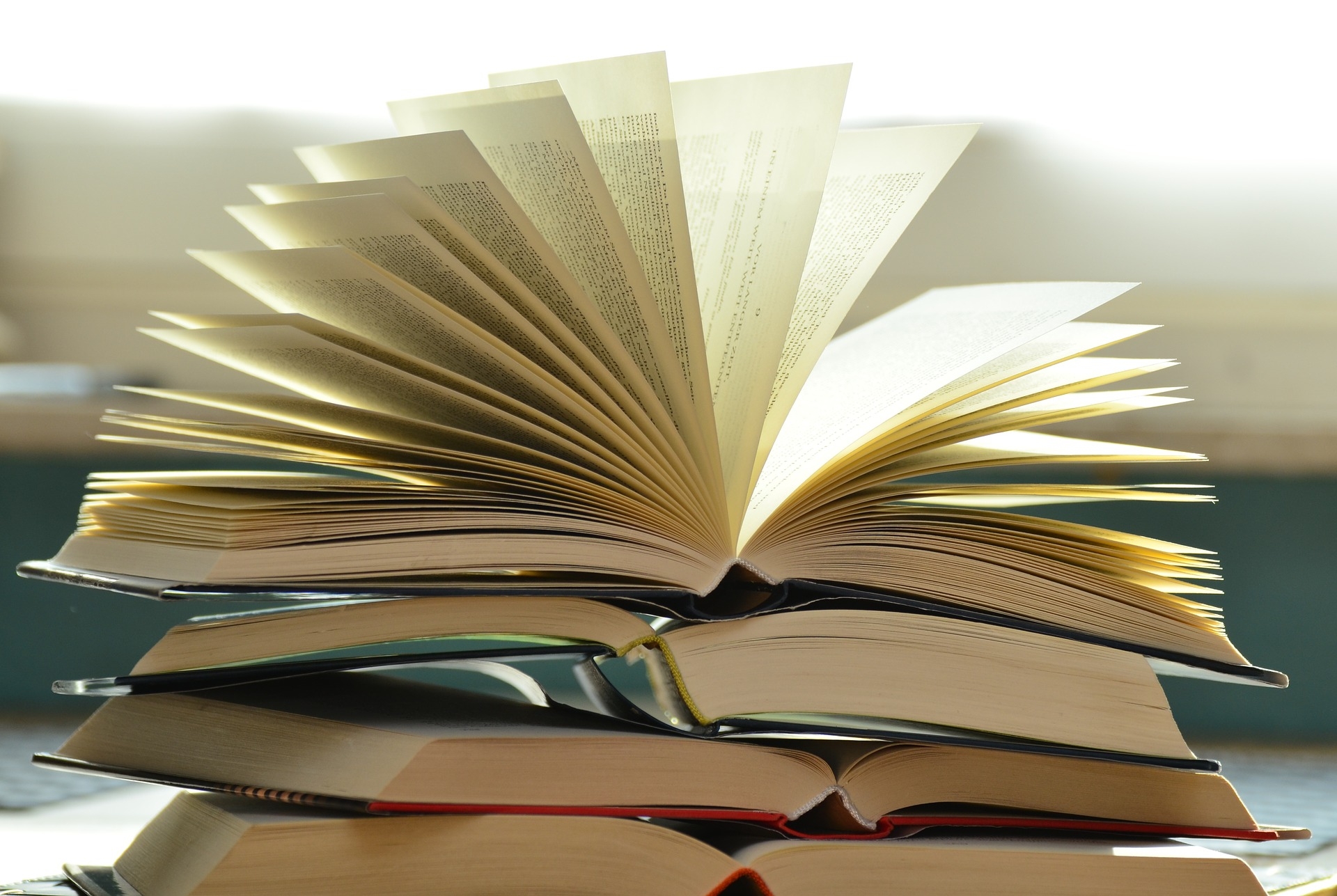
TREND
「ブランドジャーナリズム」とは?オウンドメディアのトレンド
最近、マーケティング界で再注目されている「ブランドジャーナリズム」というワード。日々コンテンツライティングに携わるみなさんのなかには、トレンドとして気になっている人も多いのではないでしょうか。
もともとこの言葉は、2004年にマクドナルド社のマーケターであるラリー・ライト氏が使ったのが始まりとされています。それが、10年以上も経た今になって再注目されているのはなぜなのでしょうか。マーケティングの新しい潮流とも言えるこの概念について、考えてみましょう。
ブランドジャーナリズムは、ブランドストーリーを語る
実を言うと、このブランドジャーナリズムという言葉には、まだ明確な定義がありません。
ただ、一般的に言われていることを公約数的に解釈すると「ジャーナリストのように、ブランドについての物語を、マーケティングや広報とは違った視点で共有する」といったところでしょうか。商品やサービスを生み出すうえで企業が持っている思い入れやこだわりなどを、ブランドストーリーとして発信することで、顧客との信頼を生み出すという手法を指しています。
読者はもう、コンテンツを信用してくれない?
このブランドジャーナリズムの手法が最近になって注目を集めている背景には、どのような理由があるのでしょうか。そこには、SNS時代のマーケティング手法として定着しつつあるコンテンツマーケティングが、実はある部分ですでに破綻し始めているというショッキングな見方があります。
コンテンツマーケティングを取り入れる企業が増え、さまざまな企業から膨大な数のコンテンツが発信されてきました。
さまざまな分野の役立つ情報が、しかも無料で配信されている。こうした状況は読者にとっても歓迎すべきことと考える人も多いかもしれません。しかし、こうしたコンテンツ全てが有益なものかと問われると、素直に「イエス」と答えられないのが現状です。
確かに、コンテンツの中には有益な情報に富み、多くの読者から支持されているものもあります。しかし、SEO観点から選定されたキーワードがふんだんに織り込まれ、読者受けするキャッチーなタイトルに彩られただけで有益な情報を得ることができない記事も決して少なくありません。他サイトの記事を参照した2次コンテンツや、セールスばかりを意識した内容の薄い記事に出会ってしまい、「どこかで読んだことがある」「面白くない」と感じた経験は、おそらく誰にでもあるのではないでしょうか。
こうしたコンテンツばかりが増えていくと、読者がコンテンツそのものに対して不信感を抱いてしまうことも否定できません。せっかく苦労して記事を書き上げても「どこかで見たようなセールス記事の一つ」と見なされ、記事を読むこと自体を放棄されてしまう危険性もあるのです。
もう一度原点に立ち返り「面白い記事とは何か」を考える
こうした事態を防ぐとして注目されているのが、ブランドジャーナリズムという考え方です。アクセス数を気にしてSEOワードばかりを並べた記事を作るのではなく、ブランドストーリーそのものを、人々を楽しませるエンターテイメント性を持たせながら発信していくことで、読者の支持を取り戻し、もう一度信頼を築き上げていくことができると期待されています。
この「読者にとって面白いコンテンツを届ける」という思考は、純粋に情報の価値を追求するジャーナリズムの考え方にも通じる部分があるといえるでしょう。
読者の信頼を取り戻すためには、企業が自分たちの都合でコンテンツを制作するのではなく、それぞれがジャーナリストとして、もう一度制作の原点に立ち返り「面白い記事とは何か」を真摯に考えていく必要があります。
こうしたブランドジャーナリズムの考え方は、もちろんコンテンツ制作に関わる私たちにとっても大きな影響をあたえるもの。むしろ、戒めともいうべき教訓を残してくれるものと言えるかもしれません。読者にとって有益で面白い記事が書けるよう、日々努力を続けていきたいものですね。
参考:
著者プロフィール

- 鈴木圭
- イタリア・ミラノ在住。広告プロダクション、出版社などを経てフリーライターに。Webマーケティングや広告デザインのほか、海外旅行やイタリア関連のコンテンツへ記事を書いている。イタリア、ヨーロッパならではの自由で面白いマーケティング事例を目にすると、ついつい楽しくなってしまう。趣味はキリム集めと、旅行先の市場でへんな食べ物を探すこと。
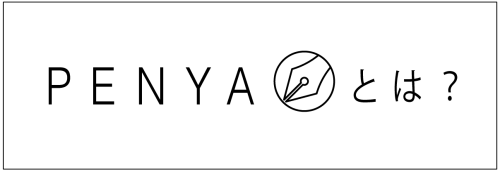

 ChatGPTに負けないWebライターになる方法とは?
ChatGPTに負けないWebライターになる方法とは?  海外在住ライター必見!「租税条約」を適用して20.42%の税率を減免できる
海外在住ライター必見!「租税条約」を適用して20.42%の税率を減免できる  Webライターが受けるインボイス制度の3つの影響とは?概要と対策を解説
Webライターが受けるインボイス制度の3つの影響とは?概要と対策を解説  編集者はツラいよ……。ライティングコーチが編集者とライターを一挙に救う!
編集者はツラいよ……。ライティングコーチが編集者とライターを一挙に救う! 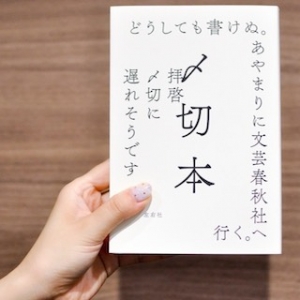 拝啓ライター様。名著『〆切本』は絶対に読まないでください
拝啓ライター様。名著『〆切本』は絶対に読まないでください