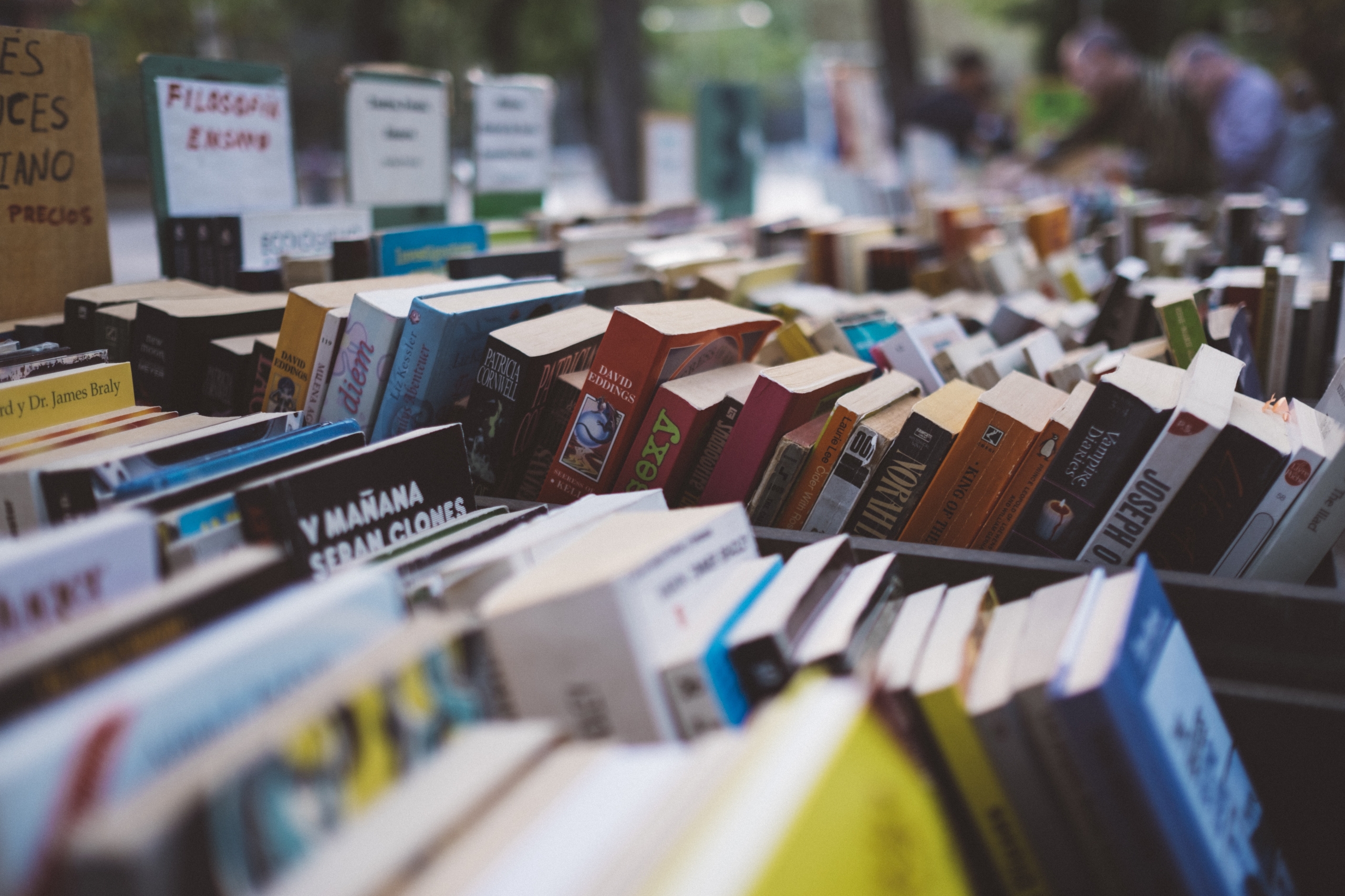
TECHNIQUE
いつか本を一冊書こうと決めている人にすすめたいシンプルな考え方
文章を書くことが好きな人であれば、いずれは自分で本を一冊書こうという目標を持っている方も多いかも知れません。
本一冊となれば、文字数は6万~10万文字程度必要になります。Webライターであれば、普段は1000~3000文字の記事を書くことが多く、まれに1万文字前後の記事を書くといった具合で、やはり慣れているのは2000文字前後の記事ではないでしょうか。ですから、6万~10万文字を必要とする本を書くことは相当に困難だ、と思われるかもしれませんね。
でも、この困難さは考え方次第で解消します。1000文字以上の記事を書ける人であれば、本を一冊書くのも不可能ではありません。どういうことでしょうか?
「自分の本」が書店に並ぶ喜び
私はサラリーマンになったころから漠然と、一生に一度でいいから、いつか自分の本を出してみたい、という夢を持っていました。
幸運なことに、会社員時代に初めて書籍化を目指して書いた原稿が、商業出版されることになりました。そして細かな経緯は省きますが、これは非常にまれで幸運なケースだったと後日知ったわけです。
出版社さんから見本として届いた初めての自分の著書を手に取ったときの手触りと重さには感動しました。また、都内の大型書店に平積みされているのを見つけたときは、「これ、私が書いたんですよ!」と周りの人に言いたくなる衝動を、一人静かに噛み締めていたものです。
このように、自分の本を出すことの喜びを知っていますので、同じような希望を持っている人には、ぜひ、出版(できれば商業出版)を叶えて欲しいと思っています。
では、実際に、本一冊を書き上げるのはどのくらい難しいことなのでしょうか。
ブログが書ければ本も書ける?
結論を先に述べてしまいますと、普段からWebライティングをこなしている人であれば、本を一冊書くことはできます。また、個人的にブログを書いているだけの人でも同様です。驚かれたでしょうか?
書きたいと思っているテーマさえあれば、実は本を書くことはそれほど難しいことではないのです。といっても、私自身はまだ5冊しか商業出版はしていません(年内にさらに3冊出版予定です)。しかし、電子書籍(ただしセルフパブリッシングですが)では10冊以上を書き上げていますので、本一冊を挫折せずに書き上げるコツはお伝えできると思っています。
先に、本一冊に必要な文字数は6万~10万文字程度だと書きましたが、これを一度に書こうとしてしまうと挫折しやすくなります。ですから、本を「小さな記事の集まり」だと考えてみるのです。既に1000文字以上の記事を書けている人であれば、その作業を60~100回積み重ねていけば6万~10万文字になりますね。
もっと簡単に考えれば、ひとつのテーマについて、毎日ブログを書くことを想像すれば良いのです。1回の投稿文字数が1000文字前後のブログを毎日更新したとすれば、2カ月から3カ月続けることで、本一冊分の原稿を書き上げられることになりますよね。
つまり、1年以上ひとつのテーマでブログを続けてきた人であれば、既に本4~6冊分の文字を綴っていたことになっているのです。
どうですか? がぜん、できそうな気がしてきませんか?
執筆の前に設計図を作ろう
ところで、文芸作品は別として、ビジネス書や実用書、自己啓発書などの商業出版が行われる際は、まず原稿より先に、企画書と目次構成案が作成されます。これらがなければ、出版社側(編集者や営業担当者)と著者側とで、同じ完成イメージに向かって本作りを行うことができないからです。
企画書と目次構成案は、いわば本作りの設計図のようなものだと言えます。そして、特に原稿執筆で重要なのは目次構成案です。最終的には編集者が多少のアレンジを行う可能性がありますが、目次構成案ができれば、一冊の本が細かな記事の集まりであることが見えてきます。
言い換えれば、本全体のアウトラインをあらかじめ考えるということですね。アウトラインとは、本の輪郭、あるいは骨子と言えます。具体的には、本のタイトル、章タイトル、節タイトル、見出しくらいまでが決められると全体像がくっきりします。
このなかでも特に重要なのが見出しです。見出しを60~100個用意することができれば、後はその見出し単位でブログ投稿一回分の記事をこつこつと書いていけば良いのです。一度に書かねばならない文字数は1000文字前後ですから、Webライター経験者やブログ経験者であれば、既に書けることが体験済みの分量ですね。
そして、目次構成案に沿って記事を書くことを積み重ねていけば、最後の見出しの記事を書き上げたときには、本一冊分の原稿が書き上がっていることになります。
どうですか? 書けそうだ、と思えてきませんか?
「100個の見出し」を用意できるかが勝負
さて、本一冊分の文字数を書くことは、実はそれほど難しいことでは無い、と想像できたかと思います。そうなると、むしろがんばりどころは、原稿を書くことよりも見出しを60~100個用意することだと気付かれるでしょう。
そうです。本を書くにあたって最も頭を捻るのは、この目次構成案を作成するときです。もっとも、こちらもブログを更新する要領で、1日1個の見出しを考え出せれば、2~3カ月で目次構成案ができあがります。毎日10個の見出しを考え出すことができれば、1週間程度でできてしまいますね。
これで、いよいよ執筆に入る準備ができました。あとは、ブログを毎日更新する要領で、記事を書いていけば本一冊が書き上げられます。ところが、書き上げた原稿を商業出版したい場合は、実は原稿以上に大切なことがあります。
それは、企画書の作成です。
出版社の編集会議(や営業会議)でその本を出版するかどうかを決める際に検討されるのは、原稿ではなく企画書だからです。極端な話、原稿がまだ無くても、企画書が編集会議に参加している方々の心を動かすことができれば、出版が可能になります。逆に、どれほど力を入れて書き上げた原稿があっても、魅力的な企画書が無ければ出版社はその原稿を見てくれません。
ですから、商業出版を目指している人は、企画書にも力を入れましょう。企画書の書き方は、また機会がありましたら紹介しますね。
まとめ
人はそれぞれ、ユニークな体験や考えを持っています。あるいはオタクやマニアと呼ばれるほどに入れ込んだ趣味であれば、専門家の域に達しているかも知れません。
一方、自分は何の取り柄も無い平凡な会社員だ、という人もいますが、その仕事や業界で身に付けたノウハウや知見は、多くの一般人にとってはお金を払ってでも「読みたい」コンテンツかもしれません。
ですから、本を書いてみたい、と思っている方は、ここで紹介した方法を参考にぜひチャレンジして欲しいと思います。
著者プロフィール

- 地蔵重樹(ハンドルネーム:しげぞう)
- ライター。ブックライティングを中心に、Webマガジンや企業のオウンドメディア、リードナーチャリング用のe-bookなどを執筆している。オカルトから経済・テクノロジーまで守備範囲が広いが、グルメとスポーツのお仕事はお断りしている。趣味は読書と、愛猫と一緒にソファーで昼寝すること。
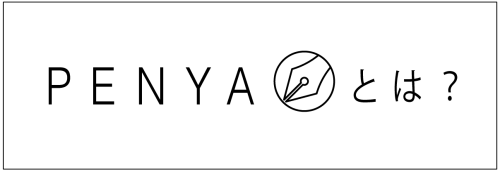

 WEBライターに必須の情報リテラシーとは?精度を高めて高単価をめざそう
WEBライターに必須の情報リテラシーとは?精度を高めて高単価をめざそう  【5分でわかる】記事のリライトとは?目的やSEO効果を高める方法を解説
【5分でわかる】記事のリライトとは?目的やSEO効果を高める方法を解説  【全ライター必見】記事執筆で音声入力を活用すべき理由とやり方を紹介!
【全ライター必見】記事執筆で音声入力を活用すべき理由とやり方を紹介!  Webライターは「WordPress」を使えたほうがいい?その理由と学習方法を解説
Webライターは「WordPress」を使えたほうがいい?その理由と学習方法を解説  マーケティングにはペルソナ設定が重要!ライティングへの活かし方を解説
マーケティングにはペルソナ設定が重要!ライティングへの活かし方を解説