
TECHNIQUE
括弧の正しい使い方
ライターの仕事をしていると、どんどん文章の表記に敏感になってきますよね。クライアントによって微妙に表記ルールが違うこともあるので、執筆するたびにガイドラインを確認することもしばしばです。
気を使わなくてはいけないことはたくさんありますが、たとえばカッコや引用符の使い方については皆さんどれくらい意識しているでしょうか?
「絶対にこうしなければいけない」という決まりはないので、記事によって使われ方がまちまちなのが実態です。でも、基本的なルールを知っておけば、迷ったときの指針になるはず!
一般的なカッコ、引用符の使い方についてご紹介します。
登場回数が多い かぎかっこ「 」
しょっちゅう原稿で使うのは、かぎかっこ「 」ではないでしょうか。かぎかっこは、主に次のような場合に登場します。
会話文や語句、文章を引用・挿入する
例:哲学者で数学者のルネ・デカルトは、「我思う、故に我あり」という名言を残しました。
会話文はもちろん、上記のような短い引用をする場合にも使います。ただし、かぎかっこでくくるには引用文が長すぎる場合、改行する、左右に空白をつくるなどして、引用部分がハッキリわかるように表記するのが一般的です。
語句を強調する
例:夫婦にとって大切なのは、「会話」です。
一部の語句を強調したい場合にも使われます。ただし、多用するとかえって読みづらくなってしまうもの。本当に必要な部分のみに使うことをオススメします。
論文名を記す
本文中や参考文献で論文を紹介する際に、論文名をかぎかっこでくくります。
ただし、参考文献の表記にはさまざまなルールが存在するので、必ずしもかぎかっこを使うとは限りません。
二重かぎかっこ『 』は強調には使わない?
次に、二重かぎかっこ『 』についてご紹介しましょう。次のような場合に使われます。
かぎかっこでくくった文章中でかぎかっこを使う
例:私は、先輩から「新入社員のうちは、特に『報連相』を大事にしたほうがいいよ」とアドバイスを受けました。
このように、かぎかっこでくくった文章の中で、さらにかぎかっこを使いたい場合にも二重かぎかっこを使います。かぎかっこを使ってしまうと、どの部分をくくっているのかわかりづらくなってしまいますもんね。
書籍や映画等のタイトルを記す
雑誌や書籍、新聞、映画、CDアルバムの名前・タイトルなどを書くときにも、二重かぎかっこを使います。
例:『吾輩は猫である』、『日本経済新聞』、『スター・ウォーズ』
「もしドラ」のようなタイトルの略称の場合は、文章の流れによっても変わってくるところです。2つ例を挙げてみましょう。
・例1:『もしドラ』は、岩崎夏海氏によって書かれた小説です。
上記のような文章の場合は、略称ですが「書籍名」として登場していますから、一般的に二重かぎかっこが使われることが多いでしょう。
・例2:『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの「マネジメント」を読んだら』という本は、「もしドラ」と略されます。
上記の文章の場合、「語句の挿入」という意味合いが強いのでかぎかっこでいいでしょう。
余談ですが、例2の文章を読んで「おや?」と思った人もいるのではないでしょうか。この『もしドラ』は、正式名称のなかに二重かぎかっこが使われているため、タイトルを紹介する際にどう表記するか悩んでしまいますね……。このような場合、執筆者・Webサイトによって表記が分かれるところです。
大手のWebメディアでも、下記のようにそれぞれ異なる表記が用いられています。
・『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら』
・「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら」
・『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの「マネジメント」を読んだら』
一部では、強調の意味で使うことも
かぎかっこより目立つということもあって、二重かぎかっこをかぎかっこと同様に強調の意味で使うケースもあります。ただし、「書籍・映画などのタイトルを記す場合や、かぎかっこを重ねて使う場合以外で使うべきではない」という考えを持つクライアントもいます。表記方法に特に指定がない限りは、強調する際は通常のかぎかっこを使っておいたほうが安全でしょう。
丸かっこ( )は補足説明
一般的に「かっこ」というと( )を想像する人が多いかもしれませんね。これは「丸かっこ」と呼ばれます。丸かっこは、基本的には補足説明をする際に使うものです。例を挙げてみましょう。
例:日経平均株価(日本国内の代表的な株価指標)は、東証一部上場銘柄のなかから225銘柄を選出して平均株価を算出したものです。
それ以外にも、「日経平均株価(にっけいへいきんかぶか)」といった具合にふりがなを入れたり、「日経平均株価(日経225)」といったように別称・略称などを入れたりすることも。出典や刊行年を記載するときにも使われますね。
ダブルクォーテーションマーク“ ”は欧文の引用符
次に、クォーテーションマークについてもご紹介しましょう。
クォーテーション(quotation)というのは、「引用」という意味。引用文の前後に置くのがクォーテーションマークです。基本的には欧文の引用をする際に使用します。
シングルクォーテーションマーク‘ ’とダブルクォーテーションマーク“ ”がありますが、一般的に日本語の記事でよく登場するのはダブルクォーテーションマークでしょう。多くの場合、「強調」の意味で使われます。かぎかっこの代わりのようなものですね。
クォーテーションマークを使うと、少し“オシャレ感”が出ることもあって、好んで使われるケースも多いです。ただし、やはり特に指示がない場合は、強調の意味でダブルクォーテーションマークを使うのは避けておいたほうが無難でしょう。
あくまで優先すべきはクライアントの表記ルール!
一般的なルールをご紹介しましたが、クライアントによって考えはまちまち。筆者は、かぎかっこの代わりとして二重かぎかっこを使用するように指定された経験もあります。
また、たとえば新聞・新聞系Webサイトでは書籍名・映画名をかぎかっこでくくることも多いようです。あらかじめ表記ルールが決められている場合や指示があった場合は、もちろんそれに従いましょう。
でも、特に何も指定されていなければ、基本にのっとって表記するのがいいですよね。そのためにも、基本的な違いは知っておきましょう。面倒に感じるかもしれませんが、細部まで気を配っていると文章の質は上がっていきます。ぜひ参考にしてみてくださいね。
著者プロフィール

- 藤澤佳子
- リクルート『SUUMO新築マンション』編集部を経て、現在はフリーランスのライター・エディター。過去の経験と保育士、ファイナンシャルプランナーの資格を活かし、主に住宅・金融・教育関係の執筆&編集活動を行う。私生活では2児の母。趣味は断捨離とコントラバス演奏。
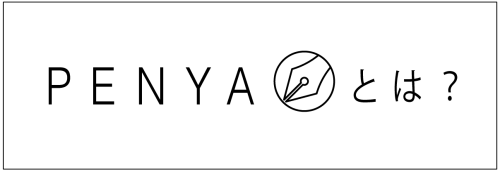

 WEBライターに必須の情報リテラシーとは?精度を高めて高単価をめざそう
WEBライターに必須の情報リテラシーとは?精度を高めて高単価をめざそう  【5分でわかる】記事のリライトとは?目的やSEO効果を高める方法を解説
【5分でわかる】記事のリライトとは?目的やSEO効果を高める方法を解説  【全ライター必見】記事執筆で音声入力を活用すべき理由とやり方を紹介!
【全ライター必見】記事執筆で音声入力を活用すべき理由とやり方を紹介!  Webライターは「WordPress」を使えたほうがいい?その理由と学習方法を解説
Webライターは「WordPress」を使えたほうがいい?その理由と学習方法を解説  マーケティングにはペルソナ設定が重要!ライティングへの活かし方を解説
マーケティングにはペルソナ設定が重要!ライティングへの活かし方を解説