
TECHNIQUE
ライターなら知っておきたい!間違いやすい日本語表現10選
私は、一人のライターとしても日々原稿を執筆していますが、編集案件では、編集者としてライターさんが書かれた原稿に目を通しています。そのなかで、「あれ、これは正しい使い方なのかな?」と思ってしまう表現に出合うことも少なくありません。
今回は、そんな気になる表現を取り上げながら、日本語のおもしろさや深さについて考えてみたいと思います。
こんな表現使っていませんか……?
では早速、間違いやすい表現が入った10の例文をご紹介しましょう!
1.たくさん練習したにも関わらず、試合に負けてしまった。
私が原稿を拝見するなかでも、赤字が多い表現です。皆さんはどこに赤字が入るかわかりますか? 実は、まだ駆け出しの編集者だった遠い昔、見落として編集長にひどく叱られた苦い記憶があります……。
正解は、「たくさん練習したにもかかわらず、試合に負けてしまった」です。ただ開いただけじゃないかと思われるかもしれませんが、この表現を漢字で表記するなら「拘(わ)らず」。ただし、平仮名で表記するのが一般的です。
実際には「関わらず」と書かれている記事も見かけるので、これから誤用とはみなされなくなるのかもしれません。とはいえ、ライターとしては平仮名で表記するほうがいいでしょう。
2.汚名を挽回する。
汚名とは、「悪い評判、不名誉」を意味する言葉。一見よさそうな感じもしますが、これも間違い。挽回するというのは、「失ったものを取り戻す」ことです。では、「汚名を晴らす」はどうでしょう。晴らすという表現は、疑いや恨みを解消するときに使われるもの。
「汚名を返上する」が正しい表現です。汚名をそそぐ(すすぐ)、でもいいですね。
3.2月の終わりに続く小春日和。
これはご存知の方が多いかもしれません。春という字が入っているので、春先をイメージしてしまいがちですが、小春は陰暦10月を指す言葉。現在の暦では11月~12月頃にあたります。季節に関する表現では、「三寒四温」にも注意が必要。
「11月は小春日和になる日が多くなりそう」など、時期に合わせた使い方をしましょう。
4.炎天下のなか、試合は開始された。
炎天とは、夏の燃えるように暑い空のことを指します。炎天下とは、そうした空の下ということ。となると、「空の下のなか……?」という、なんだかよくわからない表現になってしまいます。「満天の星空」も同じような例。満天という言葉には「空」の意味が含まれます。
「炎天のもと、試合は開始された」のほうがしっくりくるでしょう。「炎天下で」でもOKです。
5.いちばん最後に加える。
これは、料理のレシピで見かける表現。こうして一部分だけ取り上げてみると、すぐに重言(同じ意味を重ねた言葉)だと気づきそうなものですが、調子よく文章をつづっているうちに、うっかり書いてしまう方も少なくないようです。「いちばん最初」も同様ですね。
「最後」という言葉だけで「いちばん」を意味していますので、ここは「最後に加える」とスッキリさせておきましょう。
6.ビューラーを使う。
美容系ライティングで時折見かける、「ビューラー」。実は、ビューラーは商品名だということをご存知ですか? 普段使う言葉のなかにも意外な商品名が潜んでいるので、ライターは特に注意したいところ。
宅急便、万歩計、ウォシュレット、マジックテープ、QRコードもすべて商品・サービス名です。正式名称のように使われるのは、それだけ多くの人に親しまれている証なのかもしれませんね。
ちなみに、QRコードの正式名称はマトリックス型二次元コード。ちょっと覚えられそうにありません……。
さて、ビューラーの正式名称は何でしょうか? 「アイラッシュカーラー」が正解です。
7.怒り心頭に達する。
頭という文字があるので、頭のほうに向かって怒りがのぼる、それくらい怒っていることを表現するといわれればなんだか納得してしまいそうですが、どうでしょう。心頭は、「心のなか」を指す言葉。心のなかに怒りが達する……どこか不自然な気もします。
正しくは、「怒り心頭に発する」です。心のなかに怒りがわきあがると考えると、「発する」のほうがしっくりきませんか?
8.約20cmほどの長さ。
これは重複表現ですね。約20cmくらい、約20cm程度も同様に重複表現にあたります。余談ですが、校正を進めているときに記事内でこのような数字が出てきたときには、必ず元データをリサーチします。一次資料をあたってみると、実は約20cmとはいえないなんてこともあるからです。
例文は、「約20cmの長さ」もしくは「20cmほどの長さ」とスッキリさせておきましょう。
9.失敗の原因を紐解く。
「紐解く(ひもとく)」は、リード文でよく見かける表現です。「なぞを解明する」の意で使われていることもありますが、正しい表現なのでしょうか。「紐解く」の本来の意味は、書籍をあたる、もしくは書籍を読むことです。ただし、辞書のなかには、二番目の意味として「なぞを明らかにする」と載せているものも。
本来の使い方では、「紐解く」ではなく「探る」「解明する」としたほうがよさそうです。とはいえ、言葉は移り変わるもの。二番目の意味として浸透する日はそう遠くないかもしれません。
10.上には上がいる。
ライターの世界もそうです。優れた記事を読んで、自分の記事と比較してしまうことは少なくありません。上には上がいる……違和感なさそうですが、これも誤用されやすい表現のひとつ。
「上には上がある」が正解です。人を指しているわけではなく、ものを指しています。これが最高だと思っていても、さらにその上の優れたものがあるということ。立ち止まらず、さらに上を目指したいものです。
言葉に敏感なライターでありたい
なんだか偉そうにお伝えしておりますが、この10例はすべて私が実際に使ったり、最後にご紹介する書籍から学んだりしたもの。そして、表に出ていないだけで、覚え違いをしている表現はまだ私のなかにあるのかもしれません。
そう考えると、日本語って難しいなという気持ちになりますが、言葉はいきものです。はじめは誤用とされていた表現も、たくさんの人に使われることで、「紐解く」のように徐々に浸透していくことがある、そう考えると難しさよりおもしろさを感じてしまいます。
私がいま気になっているのが、「注目を集める」という表現。これは、「視線を集める」「注目を浴びる」の混用であるという意見がある一方、使っても構わないのではという意見もあり、今後どう受け止められていくのかなと密かに「注目して」います。
流行語とはまた違う、言葉の変遷。言葉の世界で仕事をしているからこそ、常に言葉に対して敏感なライターでありたいですね。
参考:
- 日本語の正しい表記と用語の辞典|講談社校閲局編
- 常識として知っておきたい正しい日本語の練習|前田安正監修/朝日新聞校閲センター著
- 朝日新聞の用語の手引|朝日新聞社用語幹事編
- てにをは辞典|小内一編
- 今さら他人に聞けない間違いだらけの日本語-あなたの日本語力を試すとっておきの100題|武久堅監修
- 知らなかったでは恥をかく!間違いだらけの日本語|一校舎国語研究会編
- 漢字で意味が変わるビミョ~な日本語|和田みちこ著
著者プロフィール

- 藤田幸恵
- 医学書の出版社勤務を経て、フリーランスのライター・エディターに。得意ジャンルは、美容・医療・薬事関連。企業の広報やECサイトの各種ライティング、紙媒体の出版物に携わる。好きな場所は図書館。苦手な場所はサウナ。
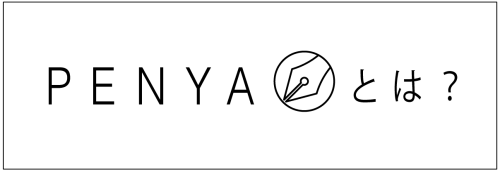

 WEBライターに必須の情報リテラシーとは?精度を高めて高単価をめざそう
WEBライターに必須の情報リテラシーとは?精度を高めて高単価をめざそう  【5分でわかる】記事のリライトとは?目的やSEO効果を高める方法を解説
【5分でわかる】記事のリライトとは?目的やSEO効果を高める方法を解説  【全ライター必見】記事執筆で音声入力を活用すべき理由とやり方を紹介!
【全ライター必見】記事執筆で音声入力を活用すべき理由とやり方を紹介!  Webライターは「WordPress」を使えたほうがいい?その理由と学習方法を解説
Webライターは「WordPress」を使えたほうがいい?その理由と学習方法を解説  マーケティングにはペルソナ設定が重要!ライティングへの活かし方を解説
マーケティングにはペルソナ設定が重要!ライティングへの活かし方を解説