
TECHNIQUE
本を出すにはどうしたらいい?商業出版のための正しい企画書の書き方とは
以前投稿した『いつか本を一冊書こうと決めている人にすすめたいシンプルな考え方』という記事のなかで、商業出版を実現するためには原稿以上に企画書が大切だと書きました。
と言いますのも、商業出版を目指した場合に、出版社に持ち込むべきは原稿ではなく企画書だからです。
なぜ企画書が必要なのか、そして企画書はどのように書けば良いのかについて、紹介します。
編集者は忙しい
さて、毎日多くの新刊が出版されていることから想像が付くかもしれませんが、出版社は常に新しい企画を求めています。
ただ、一般に公募してしまうと応募者が殺到してしまうためか、多くの出版社は表向きには企画の募集を行っていません。ウェブサイトなどでも「現在企画の持ち込みは受け付けておりません」とわざわざ明記してある出版社も多いのです。
出版社で最初に企画書を見る人は、大抵は編集者です。ところが編集者は常に忙しいですから、レベルがピンキリの企画書にいちいち目を通している時間はありません。
そのため、出版社は企画書が持ち込めるルートを限ることで、ある程度レベルが担保された企画書だけが届くような仕組みにしているのです。
企画書が通らなければ原稿は見てくれない
このように多忙な編集者ですから、ページ数が多い持ち込み原稿にまで目を通している時間はありません。
また、出版社内で行われる企画会議や営業会議でも、会議のたびに出席者全員が分厚い原稿を読んで吟味することは現実的ではありませんよね。
そこで、出版社では、まず数枚にまとめられた企画書を見て、出版するべきかどうかを判断するのです。
企画書が審査される過程は以下のとおりです。
まず、一人の編集者が企画書を審査します。この段階を通過することが最も難しいので、編集者に企画内容を認めてもらえると出版の可能性が一気に高まります。
次に、編集者が企画書を出版社独自のフォーマットに書き換えたり内容をブラッシュアップしたりして、編集会議に諮ります。
編集会議を通過しても出版社によっては営業会議が必要な場合があります。この編集会議や営業会議で企画が揉まれるのです。場合によっては練り直しを要請され、企画書を再提出します。
そうしてこれらの会議での審査を通過できれば、晴れて出版が決定します。
企画書の書き方はほぼ決まっている
それでは出版企画書はどのように書けば良いのでしょうか。
私はブックライターとして異なる出版社の企画書を見たり、私自身も著者としていくつか企画書を作成したりしていますが、記載すべき項目はほぼ同じです。
出版社側で企画書のフォーマットが指定されている場合はそれに従いますが、特に指定されていない場合は、以下の項目を記載すれば企画書として機能します。
また、項目の順序も変更して構いません。
■タイトル(※必須)
本のタイトルは、最終的には出版社が決め直すことがほとんどです。しかし企画書の段階でも、まずは編集者を惹き付けるために、インパクトのあるタイトルを考えましょう。
■サブタイトル(任意)
タイトルだけでは本の魅力を表しきれないという場合は、サブタイトルを付けておきます。
■キャッチコピー(任意)
本の帯に入れるとしたら、どのようなことを書けば読者を惹き付けられるか考えて下さい。
■概要(※必須)
本のジャンルを明らかにし、どのような内容なのかを200文字程度で表します。Amazonの「商品説明」に掲載されるような内容をイメージしてください。
■著者名(※必須)
本名を記載します。漢字の後で( )内に読み方も明記しておきましょう。
■ペンネーム(任意)
ペンネームを希望する場合のみ記載します。
■著者プロフィール(※必須)
ここはかなり重要です。テーマによっては、出版社は本の内容よりも、どのような人が書いたのかを重視する場合があるためです。
有名人である必要はありませんが、何かの専門家やマニアであるとか、ユニークな生い立ちであるとか、独特な体験をしていることなどがアピールポイントとなり得ます。
あるいは、ブログのアクセス数が半端ではないとか、営業成績が連続トップであること、ある特技でテレビに出たことがあるなど、頑張って自分がユニークであることをアピールできるものを探してみて下さい。
1000文字以内で納めると良いでしょう。
■著者連絡先(※必須)
住所、電話番号(携帯でも可)、メールアドレスなど、いつでも連絡が取れる方法を記載します。
■企画意図・企画背景(※必須)
この項目では、なぜ、この本を企画したのか。どのような社会的な背景、時代背景によってこの本が売れると考えたのかを書きます。特に以下の2点を踏まえて1000文字以内で書きます。
- なぜ今、この本が求められているのか
- この本で何が解決できるのか、どんな人(こと)の役に立つのか
■読者ターゲット(※必須)
この本を購入する読者の属性を明確にします。ここが明確なほど、出版社はその本のマーケットを予想できます。属性は以下の点に注目します。
・性別
・年齢層(例:30~40代)
・社会的立場や抱えている課題。ここは複数記載しても構いません
(例:部下を初めて持ったので指導力を付けたい管理職。子育て中で副業を探している専業主婦。できるだけ節税して相続をしたい高齢者。起業を考えている会社員。婚活中の独身男性など)
■類書(※必須)
出版社は、全く新しいジャンルやテーマにチャレンジするよりも、既に一定の市場があることが分かっているテーマを採用する傾向があります。そのために、売れている類書があれば、企画の説得力が増します。
どの本が売れているかは、Amazonのランキングやレビューの多さを参考にすれば良いでしょう。類書は2~5冊程度上げておきましょう。
■販売に有利な点(任意)
ここでは、著者自身も販売部数を伸ばすことに貢献できることをアピールします。
例えば以下のようなアピールが考えられます。
- 月間アクセス数○PVのブログを運営しているので、そこで宣伝できる。
- Twitterのフォロワーが○人いるので、本の情報を拡散できる。
- セミナーの生徒が○人いるので、販売できる。
- 著名人の○○さんのブログで紹介してもらえる。
■目次構成案(※必須)
目次構成は、企画が採用された後や執筆中に変更することがありますが、どのような本を出版したいのかを最も具体的に伝えられる部分ですので、しっかり作成しましょう。単行本1冊で60~100程度の見出しを用意し、適度な塊で章に区切る必要があります。類書の目次を見ればイメージが湧くはずです。
どこに提案するのか
さて、長くなってしまいましたが、いよいよ企画書を提出する先を探しましょう。
まず、つてがあればそれを頼りましょう。出版社に知り合いが勤めているとか、勉強会やオフ会などで名刺交換した編集者がいるなどです。編集部門ではなく、個人名を宛先にして届いた企画書は、とりあえず目を通さなければ、と思ってもらえる可能性が高いのです。
次に、ウェブ上で企画を募集している出版社があれば、そこに提出してみましょう。このとき確認しておくべきことは、募集されているのが商業出版に限っていることです。商業出版だと思ったら、実は自費出版や共同出版に誘導する募集だった、ということもありますので注意が必要です。
商業出版の募集は小さく書かれていたり、問い合わせページやQ&Aページに記載されていたりする場合があるので見つけにくいですが、私が見つけただけでも19社が募集していました。結構有名な出版社も公募していることに驚きますよ。
さて、本稿の始めの方で、編集者はある程度品質が担保された企画書だけが届くルートを持っていると書きましたが、その一つが出版コンサルタントや出版プロデュース会社、出版セミナー主催者といった出版斡旋(あっせん)業者です。これらの出版斡旋業者は、一定の水準を満たしていると判断した企画のみを出版社に持ち込みますので、編集者としては、外れが少ないと判断して目を通してくれるのですね。
出版を目指している人がこれらの出版斡旋業を利用する方法は確かに有効ですが、高額な費用を支払っても出版が保証されるわけではないことに注意してください。
彼らの仕事は、あくまでコンサルティングやプロデュース、あるいはセミナー受講であり、出版を約束するものではありません。
ただ、自分のブランディングのために投資は惜しまない、という人であれば、これらのサービスを活用するのが商業出版への最短距離かもしれませんね。
そして最後は、NPO法人「企画のたまご屋さん」のような、成功報酬型の出版プロデュースを行っているNPOに企画書を提出する方法です。
この方法では、まずNPOの審査を通過しなければならないという制約はありますが、出版されなかった場合は費用がかかりません。出版が実現したときのみ、著者が受け取る印税の一部を成功報酬として支払うという仕組みになっているためです。
ところで企画内容には出版社との相性があります。したがいまして、何社もの出版社からダメ出しされても、諦めずに企画書を出し続ける価値はあります。
以上、長くなってしまいましたが、ぜひ、面白い企画書を作成して商業出版を成功させてください。
著者プロフィール

- 地蔵重樹(ハンドルネーム:しげぞう)
- ライター。ブックライティングを中心に、Webマガジンや企業のオウンドメディア、リードナーチャリング用のe-bookなどを執筆している。オカルトから経済・テクノロジーまで守備範囲が広いが、グルメとスポーツのお仕事はお断りしている。趣味は読書と、愛猫と一緒にソファーで昼寝すること。
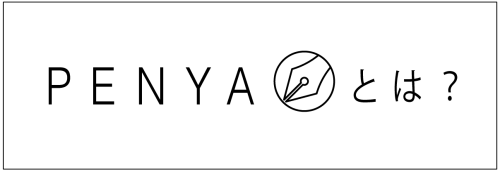

 WEBライターに必須の情報リテラシーとは?精度を高めて高単価をめざそう
WEBライターに必須の情報リテラシーとは?精度を高めて高単価をめざそう  【5分でわかる】記事のリライトとは?目的やSEO効果を高める方法を解説
【5分でわかる】記事のリライトとは?目的やSEO効果を高める方法を解説  【全ライター必見】記事執筆で音声入力を活用すべき理由とやり方を紹介!
【全ライター必見】記事執筆で音声入力を活用すべき理由とやり方を紹介!  Webライターは「WordPress」を使えたほうがいい?その理由と学習方法を解説
Webライターは「WordPress」を使えたほうがいい?その理由と学習方法を解説  マーケティングにはペルソナ設定が重要!ライティングへの活かし方を解説
マーケティングにはペルソナ設定が重要!ライティングへの活かし方を解説