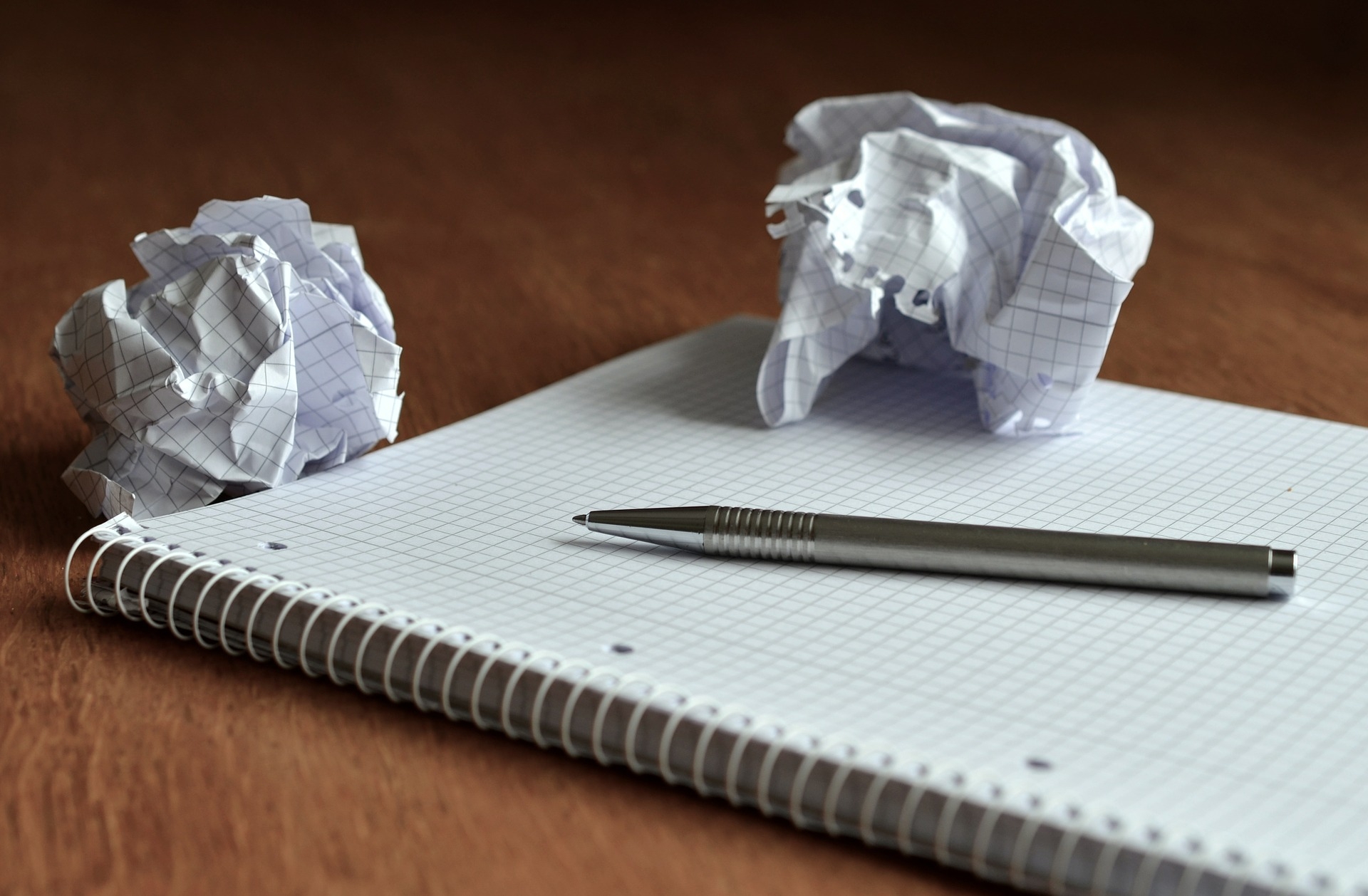
TECHNIQUE
インタビュー・取材のコツー失敗しないための準備
ライターの仕事のなかに、インタビューがあります。既にライターとして活動しているけれども、まだインタビューの仕事をしたことがないという人も多いでしょう。
そこで、仕事の幅を広げたいのでインタビューにも挑戦してみたいが、ちょっと不安、いや、かなり不安だ、という人のために、私の(決して豊富ではありませんが)インタビュー体験から、少しは役立つかもしれない「あるある」的なお話しを紹介します。
ぶっつけ本番で受けた仕事
私が初めてインタビューの仕事をしたのは、まだライターを始めたばかりのことでした。ですからインタビューなど全く経験が無かったのです。
ところが「ライター始めました」と宣言したため、早速ありがたいことに、知り合いが仕事を紹介してくれたのです。それは法人の広報誌に掲載するインタビュー記事の仕事でした。
ライターとしても駆け出しで専門の教育も受けたことがなく(未だにありませんが)、おまけに人見知りという致命的な特性を持った私が、未経験のインタビューの仕事を受けて良いのだろうか?
──と迷いはしたものの、知り合いがせっかく紹介してくれた仕事ですから、やってみよう、と思いました。
そこで「何を聞けば良いのだろう?」などと不安を持ちながらも実際に仕事を受けてみると、クライアントからインタビュー記事の構成案を渡されました。
ですから、ライターである私は、その構成案に書かれた項目に沿って質問すれば良いので、何を聞けば良いか悩む必要が無かったのですね。後は、理解できないことがあれば、臆することなくその場で質問すればいいだけでした。
つまり、このような事前に質問事項が決められているインタビューであれば、人見知りの私でも対応できると分かったのです。
ICレコーダーが必須となった
初めてのインタビューのときから、私はICレコーダーを使用しました。これは大正解でした。
というのも、私にはもともと、悪筆なうえに手書きが遅いという欠点があったからです。
案の定、実際にインタビューが始まると、相手の目を見て質問をしたり、相手の話を聞いて頷いたり、そして理解したりするのに精一杯でしたので、メモをとることが上手くできませんでした。
この辺りの状況は、私の個人的なスキルの問題ですから、メモをとることが得意な人は、ICレコーダーよりもメモの記録を重視して記事を書けばいいと思います。
ところが、初めてのインタビュー後に、録音した音声ファイルを聞きながらぞっとしたことがあります。
もし、ICレコーダーに録音できていなかったら、あるいは録音したファイルが破損してしまったら、貴重なインタビューの記録が無くなってしまうという取り返しがつかない事態になってしまうではないかと。
そこで、現在では常に2台のICレコーダーを併用するようになりました。1台はバックアップですね。操作ミスや電池切れで録音に失敗したり、音声ファイルをパソコンに転送する際にうっかり削除してしまったり破損したりする可能性もあるからです。
そのようなミスやトラブルは滅多にないことだと思いますが、バックアップがあると精神的に非常に楽になりますから、ICレコーダーを使う場合は2台用意することをおすすめします。
録音時の困ったこと
これは防ぎようがないことですが、インタビューを録音しているときに、後で再生したときにやっかいな音があることを覚悟しておきましょう。
それは、咳とカメラのシャッター音です。
インタビュー相手や自分だけでなく、同席したディレクターや営業の人など、誰かが風邪をひいていたり、咳をする癖を持っていたりすると、その咳がインタビューで交わされた会話を掻き消してしまうのです。
咳は、現場で聞いていても気になる音ですが、ICレコーダーは想像以上に強く拾ってしまいます。そのため、再生時にインタビュー相手の声に集中して耳を傾けていると、突然「ゴホンッ!!!」と鼓膜を痛めるほどの破壊的な音量と音質で咳が再生されてしまい、肝心のインタビュー内容が掻き消されてしまいます。
また、カメラマンが同行しているインタビューでは、カメラのシャッター音がインタビューを打ち消してしまいます。
現場でインタビューしている最中には気にならないシャッター音ですが、実はかなり大きな音であり、「カッシャッ!」という音の長さも結構長いのです。
そのため、再生音を聞くと、インタビュー相手が語っている内容の単語まるごとひとつくらいはシャッター音が掻き消してしまっているのですね。
従って、咳やカメラのシャッター音で打ち消されてしまった会話のところどころについては、自分の記憶や文脈から想像して補う必要があります。
まぁ、以上は防ぎようがないことなので、対策としては、掻き消された部分を思い出せるように心して聞いておきましょう、ということですね。録音しているからといって、上の空ではいけません。
座談会で発言者を聞き分けられるように
録音された音声だけを聞く際、聞き慣れた人の声であれば聞き分けることができますが、初めて会った人たちの声は誰のものか聞き分けられません。
ですから、複数の人が発言する座談会を録音する場合には、工夫が必要です。
ひとつは力技ですが、座談会を始める際に自己紹介をしてもらい、後で再生したときには、誰がどのような声質であるかをこの自己紹介の声から判断するという方法です。
ただ、これも3人程度であれば声質を記憶できるのですが、4人、5人と増えていくと、聞き分けが困難になります。
そこでもうひとつの手段ですが、もしライターが座談会の進行役的な立場であれば、逐一発言者を指名するという方法があります。
「それでは、その件について○○さんはどう思いますか?」
このように、必ず発言者の名前を声に出して録音してしまうのです。こうすれば、誰が発言しているか明快になりますね。
ブックライティングのインタビュー
インタビューのなかには、長時間かつ長期にわたって行われるものがあります。それはブックライティングで行われるインタビューです。
ブックライター(いわゆるゴーストライター)は、多くの場合はインタビューを基にして本の原稿を書き上げます。
本1冊書き上げるために必要なインタビュー時間は平均10時間程度とされています。
ところが、著者は大抵多忙ですし、人の集中力にも限界がありますから、一気に10時間もインタビューすることはありません。1~2時間程度のインタビューを数回重ねることになります。
とはいえ、ブックライティングを行う際には、出版社が練り上げた企画と構成案が先に用意されていますので、ライターはこの企画と構成案に沿ってインタビューを行います。従って、割と効率的にインタビューは進められます。
しかし、まれに構成案がないまま開始されるインタビューと執筆があります。この場合は、ともかく会話を続けて素材を集め、そこから1冊の本たり得る情報をピックアップして原稿にしていくという非効率的な作業が必要になります。
正直、このタイプのブックライティングは、かなりしんどいことになります。
また、長時間のインタビューになりますので、インタビュー相手は何度も同じ内容の話しを繰り返すことが多くなります。
しかし、同じことを書くわけにはいきませんので、ライターが誘導して別の話をさせる必要もあり、この辺りはインタビュアーとしての上手い下手が出てきてしまうところですね。
まとめ
インタビューの仕事は、現場への往復時間、事前の資料読み込み時間、インタビュー時間、そしてライティング時間と、かなり時間をとられる仕事ですから、受注金額にも注意が必要です。
勉強のために経験を積んでおきたいという段階であれば、安い単価でも受注する意義はありますが、経験を積みながら妥当な単価を設定できるようにしていきましょう。
インタビューは緊張度の高い仕事ですが、普段の生活では出会えないであろう人から直接話を聞くことができますので、貴重な体験ができる仕事だと言えます。
ぜひ、チャレンジしてください!
著者プロフィール

- 地蔵重樹(ハンドルネーム:しげぞう)
- ライター。ブックライティングを中心に、Webマガジンや企業のオウンドメディア、リードナーチャリング用のe-bookなどを執筆している。オカルトから経済・テクノロジーまで守備範囲が広いが、グルメとスポーツのお仕事はお断りしている。趣味は読書と、愛猫と一緒にソファーで昼寝すること。
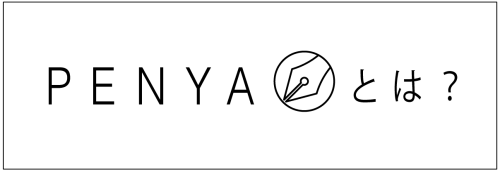

 WEBライターに必須の情報リテラシーとは?精度を高めて高単価をめざそう
WEBライターに必須の情報リテラシーとは?精度を高めて高単価をめざそう  【5分でわかる】記事のリライトとは?目的やSEO効果を高める方法を解説
【5分でわかる】記事のリライトとは?目的やSEO効果を高める方法を解説  【全ライター必見】記事執筆で音声入力を活用すべき理由とやり方を紹介!
【全ライター必見】記事執筆で音声入力を活用すべき理由とやり方を紹介!  Webライターは「WordPress」を使えたほうがいい?その理由と学習方法を解説
Webライターは「WordPress」を使えたほうがいい?その理由と学習方法を解説  マーケティングにはペルソナ設定が重要!ライティングへの活かし方を解説
マーケティングにはペルソナ設定が重要!ライティングへの活かし方を解説