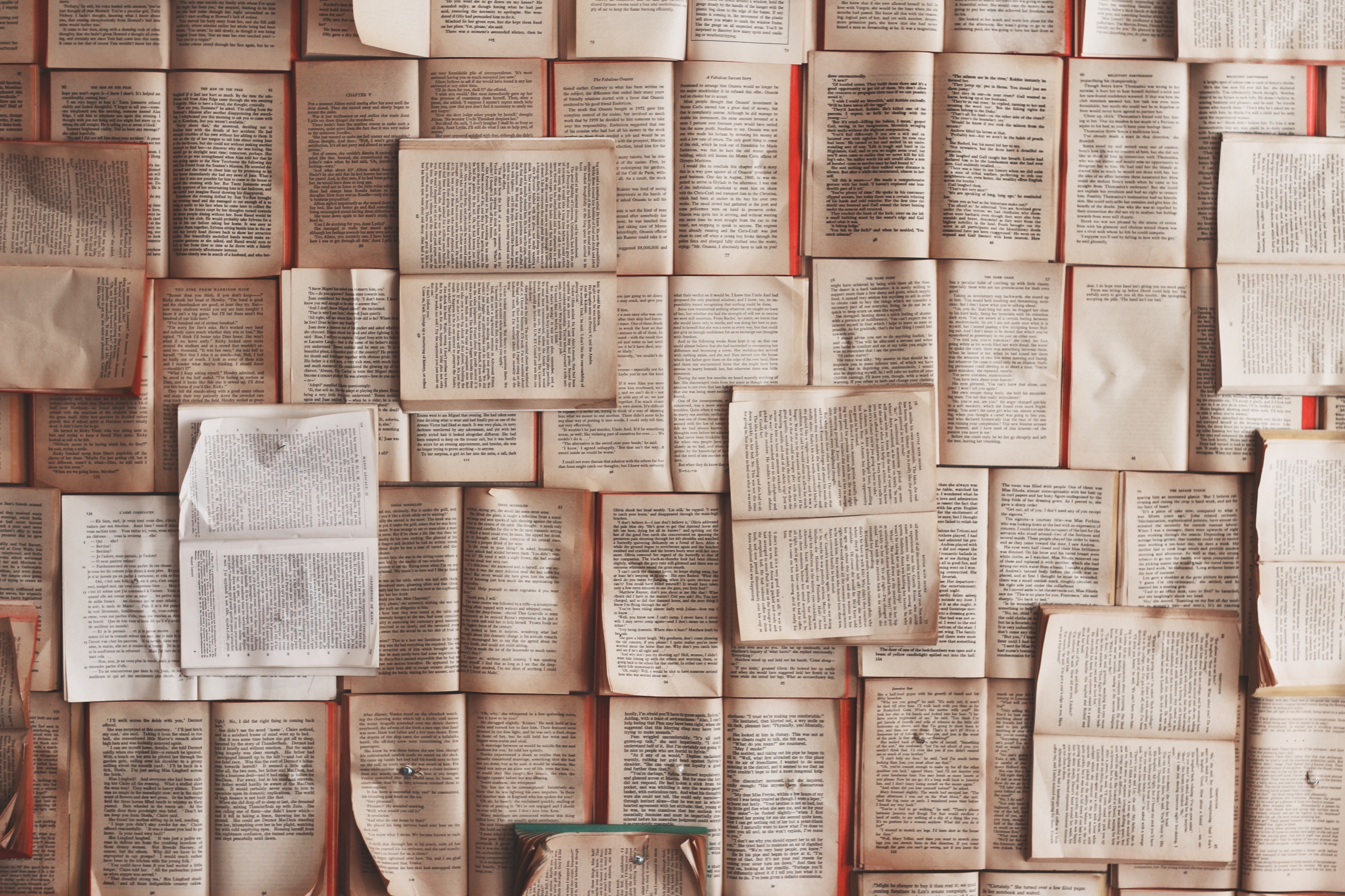
TECHNIQUE
Webライティングの基本―紙媒体出身のライターが注意するべきWebならではの書き方
Webライターを目指している人、あるいは既にWebライターとして活動している人には、文章を書くことが好きだという人は多いと思います。
いずれにせよ、書くことが好きな人は、同時に読書家であることが多いと思いますので、本や雑誌といった印刷媒体上の文章を読むことが多いかもしれません。
そこで今回は、印刷媒体上の文章に馴染んでいる人ほど注意しなくてはならないWebライティングの注意点について紹介しましょう。
読書家ほど陥る罠
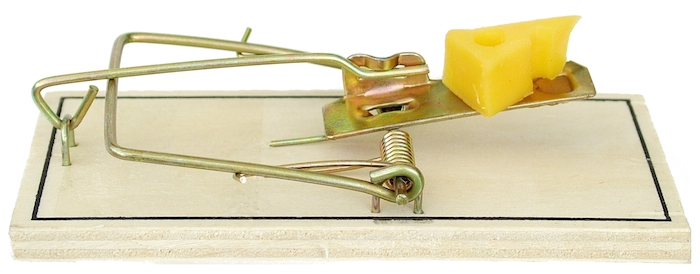
Webライターとはいえ、「ライター」を名乗るからには、普段から読書をすることで良質な文章に多く触れるようにしている人も多いでしょう。
しかしそこに、読書家ならではの陥りやすい罠があります。
読書家ほど良質な文章に触れているはずですが、うっかりすると、印刷媒体だからこそ効果的となっている文章の書き方を、Webライティングにも持ち込んでしまうことがあるのです。
先日、Webライターの募集広告のひとつに、「印刷媒体出身ライター不可」と明記されているのを見つけて驚きました。そこまで嫌うか?──と。
その募集広告では「不可」の理由が書かれていませんでしたので、印刷媒体で身に付けた癖がWebライティングでは仇となることを避けようとしていたのか、単価の相場観が異なる(印刷媒体はWeb媒体より一般的に高い)ことを嫌ったのかは分かりません。
それはともかく、WebライターのライティングにはWeb媒体特有の注意点があることは確かです。
それでは、印刷媒体(特に本)と比較して、Web媒体でのライティングの注意点を確認しておきましょう。
印刷媒体と比較したWeb媒体でのライティングの注意点

印刷媒体に慣れた読者が、Web媒体用にライティングをする際には、以下のような注意が必要になります。
●情報は早めに提示する
まず、回りくどい言い回しは避けましょう。
これは、私自身が陥りやすい罠なので自戒も込めて書きます。
印刷媒体の代表である本は、読者に対する拘束力が強い媒体です。本は何冊も持ち歩けませんから、一旦読み始めると多少前置きが長くても、期待感を持ちつつ我慢して長文を読み続けてくれます。
一方、Webサイトの閲覧者は本の読者とは異なり、クリックひとつ、あるいはタップひとつで気軽に世界中のほかのサイトに移動できます。
つまり、Web媒体は閲覧者に対する拘束力が弱いということですね。したがって、早めに閲覧者が欲しがっている情報を提示する必要があります。
●スクロールは少なめが読みやすい
情報商材の販売サイトなど一部のマーケティング手法では、わざと何度もスクロールしないと核心に迫れないような焦らし効果を狙ったサイトを作成しますが、この手法は例外的だと考えた方が良いでしょう。
一般的なWebサイトでは、スクロールをし続けなければ欲しい情報にたどり着けない長文は避けるべきです。どうしても長くなる文章では、サイトを分割してページをめくるような工夫が必要になります。
●Webコンテンツはさまざまな環境で閲覧される
そしてWebサイト用の文章を書くときは、さまざまなデバイス環境で表示されることを意識しましょう。
印刷物は紙に印刷された段階で、書体や文字サイズ、レイアウトなどが完全に固定されますので、全ての読者に同じ状態の書体や文字サイズ、レイアウトを表示できます。
一方、Web媒体はOSやブラウザの種類、デバイスのディスプレイサイズなどによって表示のされ方が変わってしまいます。特に、最近ではスマートフォンで閲覧されたときに読みやすい文章が求められます。
そのため、ニュースサイトなどでは1段落中の文字数制限や、段落と段落の間には空行を入れるといった規定が設けられていることがあります。
また、限られた環境でしか正しく表示されない記号を使うことも止めましょう。
キーワードの重要性
Web媒体では検索キーワードが非常に重要な役割を果たします。ネット上で情報を探している人は、キーワードで検索するためですね。
ですから、印刷媒体では効果をもたらす技巧的な表現が、Web媒体では仇になる可能性があります。
たとえば、リーフレットやポスター、雑誌の広告ページでは、実際に目にした人の注意を惹くために「コンペチターをクールに出し抜け!」と大きな文字で書かれていれば、「何だろう?」と思って続きを読んでくれる可能性があります。
すると、SFA(Sales Force Automation:セールスフォース・オートメーション)と呼ばれる営業支援システムの広告記事であることがわかります。印刷媒体であれば、何を意味しているのか分からないタイトルやキャッチコピーでも、印刷物をまず目にしてしまうので、その奇抜さで本文に誘導することが可能です。
しかし、ネット上では欲しい情報をキーワードで検索しますので、「SFA」や「Sales Force Automation」、あるいは「営業支援システム」といったキーワードを前面に出したタイトルやキャッチコピーが必要になります。「クール」や「出し抜け」で検索する人はほとんどいないためです。
ですから、Web上ではトリッキーな表現を使う以上に、情報を探している人が使うであろうキーワードをタイトルや見出し、あるいは本文に入れることに注意する必要があります。
SEOの基礎の基礎だけでも知っておく

以上、印刷媒体に馴染んだ人がWebライティングで注意すべきことの一部を紹介しましたが、やはりWebライティングの仕事を受注していこうと思っているのであれば、SEOの基礎的な知識を知っておくべきでしょう。
SEO(Search Engine Optimization)は「検索エンジン最適化」などと訳されていますが、要するにGoogleなどの検索サイトで、特定のキーワードで検索された際に、できるだけ上位に表示されるように工夫する技術です。
SEOは非常に奥が深い技術ですから、本格的に勉強しようとすると、辞書ほどの厚みがある専門書を読まねばなりません。ですから、ライターとして必要最低限の知識を得るためには、ネット上で調べたサイトの記事で、理解できるものをいくつか読んでおけば良いでしょう。
そうしておけば、クライアントから「タイトルの頭に指定のキーワードを入れてください」や、「本文中に指定のキーワードを○回~○回入れておいて下さい」との要請を受けたときに、その意味が理解できます。
なかには「SEOを意識して書いてください」といった、かなりアバウトな依頼もありますが、SEOの基礎知識があれば、なんとか対応できるでしょう。
まとめ
読書家ほど、Web媒体のライティングでは陥ってしまう罠があることを紹介しました。
しかし、ライターが文章を書く人である以上、常に多くの本を読んでさまざまな文章に接することは良いことだと思います。また、読書から得られる知識や考え方は、ライターとしての引き出しも増やしてくれることが期待できます。
問題は、媒体によって書き分ける「技術」というほどのものではなくとも、「意識」は持っているべきだと言うことですね。
著者プロフィール

- 地蔵重樹(ハンドルネーム:しげぞう)
- ライター。ブックライティングを中心に、Webマガジンや企業のオウンドメディア、リードナーチャリング用のe-bookなどを執筆している。オカルトから経済・テクノロジーまで守備範囲が広いが、グルメとスポーツのお仕事はお断りしている。趣味は読書と、愛猫と一緒にソファーで昼寝すること。
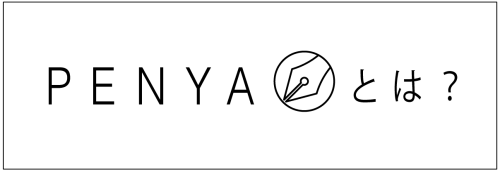

 WEBライターに必須の情報リテラシーとは?精度を高めて高単価をめざそう
WEBライターに必須の情報リテラシーとは?精度を高めて高単価をめざそう  【5分でわかる】記事のリライトとは?目的やSEO効果を高める方法を解説
【5分でわかる】記事のリライトとは?目的やSEO効果を高める方法を解説  【全ライター必見】記事執筆で音声入力を活用すべき理由とやり方を紹介!
【全ライター必見】記事執筆で音声入力を活用すべき理由とやり方を紹介!  Webライターは「WordPress」を使えたほうがいい?その理由と学習方法を解説
Webライターは「WordPress」を使えたほうがいい?その理由と学習方法を解説  マーケティングにはペルソナ設定が重要!ライティングへの活かし方を解説
マーケティングにはペルソナ設定が重要!ライティングへの活かし方を解説