
TECHNIQUE
文章力のポイントは「直し」にあり。3ステップの原稿見直し術
提出前の原稿を見直すとき、みなさんはどんなことに気をつけていますか? 何度もチェックしてもなかなか誤字がなくならない……そんな悩みをもつ人も多いかもしれません。校正ツールを活用するのもひとつの方法ですが、もしライターとしてのスキルを上げたいなら、原稿を自分で校正する力をつけることをおすすめします。
今回は、原稿の見直し時に注意すべきポイントを3つのステップに分けてご紹介しながら、記事の質を上げる方法について考えます。
STEP1 誤字脱字を見つけ出せ!
まず、知っておきたいことがあります。それは、誤字脱字をゼロにするのは簡単ではないということ。
私自身、編集者としていろんな原稿を拝見しますが、誤字脱字が全くない人は残念ながら少数派です。ただ、ゼロの人は一貫してゼロ。たまに誤字を見つけると、うれしくなってしまうくらいにゼロです。
なぜこんなに違いが出るのでしょう。それは、原稿の見直し方にあると私は考えます。
原稿を何度見直しても、視点が変わらなければ間違いを見つけることはできません。
原稿を見直すときに必要なのは、筆者ではない「第三者の目」です。
その原稿をはじめて読む人になりきって読んでみてください。ミスはないはず、という思い込みを捨てるのがポイントです。ライターが見逃した誤字を編集者や校正士が指摘できるのは、もちろんスキルもありますが、第三者の視点がもたらすところも大きいのではないでしょうか。
さて、第三者の目に切り替えることができたら、同時に以下のポイントに注意して原稿を読み直します。
- ひらがなが連続している箇所
- 後から書き直した部分
- タイトル、大見出し、小見出し
- ナンバリング
- 同音異義語
- カタカナ・アルファベット表記(特に英単語そのままのもの)
なかでも、上記は見落としが起きやすい箇所です。ひらがなが連続している場所は、タイプミスが多発。できれば声に出して読み直すといいですね。タイトルや見出しを間違えるわけがない……そんな思い込みが見落としを招きます。カタカナの専門用語も転記ミスが多くなりがちなので、できればコピー&ペーストをおすすめします。
誤字脱字をゼロにする最も確実な方法は、当然ながら執筆段階でのミスをなくすこと。
上記のポイントに気をつけながら原稿を執筆できれば、それがベストです。校正ツール任せにならないライティング力を身につけたいですね。
STEP2 読みにくい表現をチェック!
さて、ここからは記事のマイナス点を取り除く方法ではなく、記事の質を上げるための見直し術についてお伝えします。
気合いを入れて書いたのに、原稿が真っ赤になって返ってきてショック……そんな経験をもつ人は多いでしょう。でも、その赤字には、スキルアップのヒントがたくさん隠れています。赤字が多くなる原因はさまざまですが、なかでもよくあるのは「内容の薄さ」、そして「文章の読みにくさ」です。
内容の薄さについては追加のリサーチが必要ですが、読みにくさは見直しの段階で十分フォローできます。
特にチェックしたいポイントは以下の通りです。
- 「など」「~も」の多用
- 文末表現の重複
- 同意を押しつける表現
- 体言止めの使い方
ネット上の記事は、偶然たどり着いて読まれることも多いもの。ちょっとでも読みにくさを感じると、読者はすぐ違うページに移動してしまいます。
例えば、「~です」が連続すると、文章がブツブツ切れている印象を与えますし、そうは思わないのに「~ですよね」と同意を促されると、それ以上読み進める気持ちがなくなってしまうことも。体言止めを適度に活用するのは、文章の流れをつくるうえでよい方法ですが、使い方を間違えるとかえって読みにくくなるので注意しましょう。
STEP3 記事全体に目を向けよう!
最後は、記事全体の見直しです。アウトラインに沿って執筆していたはずなのに、勢いあまってつい横道にそれてしまうことはありませんか? 私はよくやってしまいます……。
そんなときに特に気をつけたいのが、以下の3つのポイントです。
- 情報を知っている前提で書かれていないか。
- クライアントの希望に沿っているか。
- 見出しと見出しのつながりはスムーズか。
リサーチをすればするほど、記事のテーマに対する理解は深まります。ただし、その勢いで執筆すると、情報を知っている前提の記事になってしまい、読者が置いてけぼりになるので注意が必要。
昔読んだ本で、「原稿を書くときは、一人の人物を想定して書いたほうが伝わる文章になる」と教わったときから、架空の人物を頭において文章を書き進めるようにしています。つまり、ペルソナの設定です。そうすると、読者が何を知らないのかを考慮した記事になり、わかりやすさもアップするように思います。
時々、それぞれの見出しが完全に独立しているような原稿を拝見しますが、そうなると最後のまとめだけではまとめきれなくなることも。
そんなときは、「では次に、~について考えてみましょう」というような橋渡し役となる文を差し込むと、記事全体の流れがスムーズになるでしょう。
その見直しが、スキルアップへの第一歩
執筆のクセも、仕事の進め方も、10人いれば10通り。必ずしもこれが正解という方法はないかもしれません。見直しなんて面倒だし、私はスピード重視という人もいるでしょう。
もし、もっと稼げるライターになりたいと思うのなら、執筆本数を増やすのもひとつの手ですが、記事の質を上げるのもまたひとつの手です。どんなに頑張っても、記事を書くスピードには限界があります。
では、記事の質はどうでしょうか。実力次第で、きっとその可能性はどんどん広がっていくはずです。
ご紹介した見直し術は、そのまま記事を校正する力につながります。校正士や編集者の仕事にも活用できますし、自分で原稿をきちんとチェックできれば、編集者いらずのライターになり、記事の単価も必然的に上がるでしょう。
最後に。第三者の目に切り替えるうえで、とっても手軽な方法があります。
それは、原稿を一晩寝かせること。
翌朝、新たな気持ちで原稿を読み直すと、とんでもない間違いを発見することが多々あります。なかなかミスがなくならないとお悩みの人は、ぜひ試してみてくださいね。
著者プロフィール

- 藤田幸恵
- 医学書の出版社勤務を経て、フリーランスのライター・エディターに。得意ジャンルは、美容・医療・薬事関連。企業の広報やECサイトの各種ライティング、紙媒体の出版物に携わる。好きな場所は図書館。苦手な場所はサウナ。
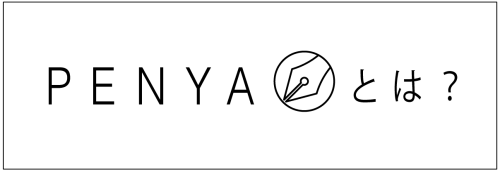

 WEBライターに必須の情報リテラシーとは?精度を高めて高単価をめざそう
WEBライターに必須の情報リテラシーとは?精度を高めて高単価をめざそう  【5分でわかる】記事のリライトとは?目的やSEO効果を高める方法を解説
【5分でわかる】記事のリライトとは?目的やSEO効果を高める方法を解説  【全ライター必見】記事執筆で音声入力を活用すべき理由とやり方を紹介!
【全ライター必見】記事執筆で音声入力を活用すべき理由とやり方を紹介!  Webライターは「WordPress」を使えたほうがいい?その理由と学習方法を解説
Webライターは「WordPress」を使えたほうがいい?その理由と学習方法を解説  マーケティングにはペルソナ設定が重要!ライティングへの活かし方を解説
マーケティングにはペルソナ設定が重要!ライティングへの活かし方を解説